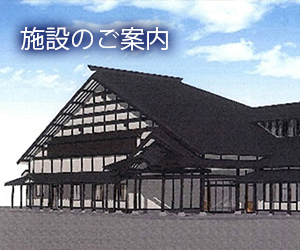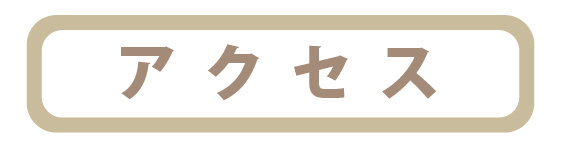~二階講中
○番楽の知識もまだ浅い私ですが、何度か同じ演目を観る機会に恵まれて、この「三番叟」もその一つです。舞手の所作の違いや掛け唄・囃子によって地区ごとの味わいがあり、飽きる事なく観させていただいております。「本海番楽(鳥海町教育委員会編集・平成12年3月発行)」に各講中の言い立てが掲載されており、これが結構面白いのです。二階講中の出だしは『よ~しだのによしだの~に』。 猿倉講中は『君を始て拝ムレハ~』。同じ人が作って、同じ人から習ったはず、ですが・・・ そう思うとなかなか興味深い。詩を変えて、編曲して、振付も変えて、色んなことして楽しんでたんだな~、と勝手な解釈をしています。本海坊さんはお坊さんにしておくのが勿体ない、総合プロデューサーだったのでしょうか。二階講中の言い立てだけで30演目からありました。これを当時の方々が文字に起こした事も、大したものだと感心します。
○今年のお正月公演に「伊加」「もちつき」でデビューしたご兄弟。10か月ぶりの再演やいかに?と楽しみにしておりました。前回は「いか」とはなんぞや?に触れましたが、今回は舞に集中しておりました。なんとジャンプの多いことか。最初の着地で舞台が滑ったように見えたので、ちょっと心配していました。後半ともなると演者の荒い息が聞こえ、お客さんも「応援」の心情で見守っていたようです。得てして番楽には体力勝負の演目が多々あり、その度に応援の拍手を送りながら「若くなきゃ続かん」、と自分に置き換えるのが常です。存続には絶対若手が必要なのです!
「もちつき」は道化舞でお客様を楽しませる曲です。これも前述の「本海番楽」で勉強しました(偉?)・・・餅をつくには「えづら(合いの手)」 が要るので、お客さんに手伝いを頼むが断られてしまう・・・というストーリーです。早速客席におりてお客さんの手を引っ張る~声をかけられお客さんも嬉しそう!~「それでは」と立ち上がりそうなお客さんに、『お願いしながらも、こっそりお断りする』という見事なテクニックを披露。これにはスタッフが一言「お、やるじゃん!!アドリブできてる!」


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
~萱ヶ沢番楽
○赤田長谷寺の是山和尚が祖とされる萱ヶ沢番楽。「番楽(三番叟)」は同じ演目名でありながら所作が別物で興味深く拝見しました。それから神舞の所作に、(決して他意はございません)マイケルジャクソンの月面ウオークに似た足使いがあって、発見した喜びにひとりほくそ笑んでいました。それにしても、柔らかな足の運びと、刀をスパッと振り抜く潔よさ。緩急織り交ぜての舞で楽しませていただきました。

○獅子舞 ずっしりと重そうな獅子頭を恭しく持ち上げたかと思うと、パン!と力強い歯打ちの音にお客さんから「ほおっ!」という声が出ました。前出の演目は少し娯楽要素が感じられましたが、この獅子の登場に一瞬空気が引き締まりました。獅子の存在感は格別ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
~鳥海山小滝舞楽保存会
○本日は正に獅子舞と番楽の日でした。『とおりの楽』を奏でながら入場されたご一行。舞台の主任(とり)を務める「御宝頭の舞」はそのお役にふさわしく重厚な舞でした。宮司さんの御祈祷から「神様」への信仰が感じられ、御獅子様がお祓いをしてくださる時は、お客様共々自然に頭も下がりその恩恵を頂戴しました。・・・そして頭を上げたとき心なしか清々しい気持ちになり、自分の汚れが祓われたお陰かなと妙に納得したところです。ごく自然にこの動作ができるのは日本人たる所以でしょうか。

 舞が進み、獅子が咥える刀を後幕の方が鞘から抜く場面がありました。それがとても自然で、舞手は既に獅子に同化しているかのようでした。 宮司、お囃子、舞手の方々の所作がとても丁寧で、厳かな佇まいに心も安らいだ時間でした。
舞が進み、獅子が咥える刀を後幕の方が鞘から抜く場面がありました。それがとても自然で、舞手は既に獅子に同化しているかのようでした。 宮司、お囃子、舞手の方々の所作がとても丁寧で、厳かな佇まいに心も安らいだ時間でした。

・・・・・・・・・・・・・
本日は大潟村から50名を越える団体のお客様をお迎えしました。この公演と鳥海の紅葉を楽しみに来町されたとのこと。お帰りの際には「今日はいいものを見せて貰った」と口々にお話されていかれました。
~~ありがとうございます! お客様の「その声」が何よりのご褒美です!!
※12月は諸般の事情により定期公演をお休みいたします。ご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。正月公演にて皆様のお越しをお待ちいたしております。お体に気を付けてお過ごしくださいますようお祈り致します。